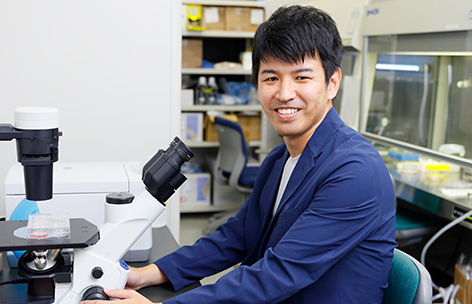日本が直面する生産年齢人口の減少という課題に独自のアプローチを提案する
奈良先端大は文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択され、「生産年齢人口減少社会の自動化・省力化技術とこれを担う博士人材育成で社会変革を先導する大学院大学」を10年後のビジョンとして、我が国の大学や産業界が直面する喫緊の課題の解決に向けたプロジェクトに取り組んでいます。その戦略として「東南アジア諸国からの戦略的な人材リクルートと輩出」「自動化・自律化とデータ共有による研究力と社会実装の強化」の2つを掲げています。
そこで、J-PEAKS申請ワーキンググループのメンバーとして提案を取りまとめたバイオサイエンス領域の中島敬二教授(J-PEAKS担当学長補佐)、物質創成科学領域の上久保裕生教授、データ駆動型サイエンス創造センターの藤井幹也教授、情報科学領域の林優一教授に戦略の意義や10年後への展望について語ってもらいました。
人材バンクや研究の自動化・省力化のシステムを構築
―令和6年度の公募で全国の65大学から申請があり、奈良先端大を含む13大学が採択されました。5倍の競争率はかなりの難関でしたが、採択に至るまで、どのような経緯がありましたか。
中島教授 先端科学に特化した研究大学院である本学が研究力強化のための文科省のプログラムに入らないことは、大学にとって危機的な状況になると感じました。まず「絶対に採択されなくてはならない」とワーキンググループで確認しました。公募前の昨年2月から年末のサイトビジットまでの1年間、検討に検討を重ね、申請書類やプレゼン資料の手直しが提出日の朝までかかるなどの切迫した状況が続きました。採択されたことは喜びでしたが、採択後には大仕事が待っていることもわかっていましたので、むしろ「1年間の苦労が無駄にならなくてよかった」という気持ちの方が強かったです。
―採択された奈良先端大の提案は、本学の研究の特色や実績、組織力をどのように反映させていますか。
中島教授 本学は、先端科学技術研究科という1研究科体制の中で、情報科学、バイオサイエンス、物質創成科学の3領域の研究が行われています。なかでも持続可能な社会を実現するための課題に取り組む研究者が多く、その分野の研究力が強いのが特徴です。また、小規模大学ならではの機動力を活かして、さまざまな改革を先頭に立って迅速に成し遂げてきた実績があります。
そこで、これらの特徴や強みを活かし、日本が直面する最大の課題である「少子化による生産年齢人口の減少」に取り組む「10年後のビジョン」を考えました。具体的な戦略は2つあります。1つ目は、日本の産学で活躍が期待される海外出身の優秀な人材を育成する取り組みです。海外の連携大学との豊富な交流実績を基に、日本と経済的・文化的な関わりが深い東南アジアから優れた研究人材を組織的にリクルートして、日本人学生と一緒に国際的視点をもつ研究・開発人材を育成します。さらに「NAIST人材バンク」を創設し、就活時の産官学との効果的なマッチングを推進します。
2つ目の戦略は、「研究の自律化・自動化と、高度な情報セキュリティに守られたデータ共有システム」の構築です。研究開発の自動化やAIを用いた自律化は、Automated Research Workflow、略してARWと呼ばれ、国際的な関心や経済界の投資意欲が急速に高まっています。生産年齢人口の減少という問題に直面する日本の産業界でも、企業の関心が高まりつつありますが、公的資金による開発投資は遅れています。本学では、この考えを普段の研究活動に取り込むとともに、本学の研究が日々生み出すデータを産業界が安心して検索できるセキュアなシステムを作ることで、効率的な社会実装につなげる仕組みを作ることを目指しています。研究の自動化・自律化を意味するARWに、社会実装Industrial Translationを意味するITを合わせたARWITという言葉を冠した「ARWIT System」を構築し、産学で共有することが目標です。

海外の大学との連携を強化し、研究力の強みを生かした社会実装のシステムを構築する
―まず「東南アジア諸国からの戦略的な人材リクルートと輩出」の戦略については、どのようなところが実現のポイントになるのでしょうか。
中島教授 まず、優秀で日本社会に親和性をもつ人材をいかに選抜するかが重要なポイントになります。本学はすでに「留学生特別推薦選抜制度」を導入し、海外の連携大学から推薦された人材を予備選抜しています。また、本学の教員が連携校に出向いて広報やリクルート活動を行っています。連携先の教員だけでなく、本学を卒業した留学生の同窓会や、その国の教育機関や官庁との信頼関係に基づく組織的な連携を一層、密にする努力が大切です。
もう一つの重要なポイントは、キャリア支援です。本学では「キャリア支援室」が、留学生を含めた全学生の就職活動をサポートしていますが、特に留学生に対しては、グローバルなネットワークをもつ特任教員の先生がきめ細かな就職支援をしています。この取り組みをさらに強化するために、本学が輩出する人材の情報を提供する「NAIST人材バンク」を設立します。産官学の担当者が情報にアクセスし、留学生の希望やスキルにかなったマッチングを可能にすることで、日本で活躍する場を提供します。
―「自動化・自律化とデータ共有による研究力と社会実装の強化」の提案は、3領域の強みを活かし、連携する戦略です。簡単に言えば、バイオサイエンス領域が研究シーズの発掘や生理活性物質の自動スクリーニング、物質創成科学領域が、AIを用いた新規マテリアルの自動設計や自律合成、物性データの自動計測を担当します。そして情報科学領域が、研究データの蓄積や分析、外部機関とのセキュアな共有を進めるための「データ流通プラットフォーム」の構築を担います。それぞれの領域でどのような点を重視されていますか。
中島教授 バイオサイエンス領域は、研究シーズを創出する段階の担当で、将来の発展可能性や市場価値が高いと見られる素材のスクリーニングを自動化します。本学は、再生可能資源である植物バイオマス、廃棄物による環境汚染を未然に防ぐ生分解性樹脂などさまざまな研究が行われており、そのなかで、あらかじめ有効性を自動的に見極め、省力化することで、効率的な社会実装につなげます。
上久保教授 物質創成科学領域の役割は、最先端の研究シーズを自動的に社会実装できる具体的な物質に変換し、開発するためのデータを創出するところにあります。そのためには、自動合成、自動計測、自律設計の技術が必要で、本学の強みである研究システムのRX(リサーチ・トランスフォーメーション)化などを進めながら、それぞれの技術を一本化することで、確実なデータを取得できるようになります。自律的研究推進という課題に応えるための、新たなモデルを提示します。
藤井教授 本学のJ-PEAKSの取り組み自体に、生産年齢人口の減少という問題意識があります。その解決策として留学生のリクルートや人材育成に加えて、研究を自動化し、省力化するというところはとても大事だと思っています。ただ、最近のAIの発展を見ていると、AIを使い尽くすことにより、テクノロジーに頼るだけでなく、人の意識が変わり研究力の向上に結びつく例が多くみられます。この興味深い現象も、人材不足を補う糸口になると思います。
例えば、研究以外の例になりますが、デジタル技術で作成されたバーチャルな歌手の初音ミクが登場し、大ヒットしたことによって、「デジタル技術の合成音でしか歌えない」と思われていた歌を、若手の歌手が練習してマスターし、歌唱力が飛躍的に向上しました。デジタル技術の進歩が契機となって、個人の意識が変わり、発展していく。私はAIに実験の条件を設定させ、ロボットに材料を自動合成させる研究などを続けていますが、学生や若手研究者、企業の研究者らが、新しい科学の形に魅せられて、能力をどんどんアップデートしていくところを間近に見て、このことを確信しています。
林教授 ARWITでは、3つの領域が一体となってプロジェクトを推進する必要があります。その中で情報科学領域は、情報セキュリティ技術を提供する役割を担っています。本分野は情報科学領域の強みの一つであり、開学当初から高く評価されてきました。さらに、複数の学問分野が交差・融合して発展してきた学際的な領域でもあります。これまでに蓄積した知見を用いて構築される「セキュアなデータ流通プラットフォーム」は、本学の3領域を横断的に結び付ける融合基盤として機能することが期待されています。
また、J-PEAKS事業の基本方針には「研究力を核とした経営戦略」が掲げられており、その観点からも、大学が保有する研究シーズデータやARWITシステムで創出されるデータを活用した収益化は戦略的に極めて重要です。そのためには、データの「来歴」を保証し、利用者が安心して活用できる環境を整えることが不可欠です。私たちは、この環境を実現するために最先端のセキュリティ技術を導入してゆきます。
一方で、先端的な研究を行う企業や研究機関では、自らがどのようなデータにアクセスしているかを他者に秘匿することも求められます。こうした要請に応えるため、高度な暗号技術を活用し、検索クエリやアクセス履歴を、データベース管理者に対してすら秘匿できる仕組みの実装を進めています。
現在、大学や企業が保有する研究シーズデータの約99%は死蔵されていると考えられています。ARWITは、こうした未利用データの利活用を促進することで、知的財産を保護しながら活用できる仕組みを提供します。これにより、データを提供した者が、安心して利用者と共有できる環境を整備します。これに加えて、利用頻度に応じたインセンティブを付与する仕組みの導入も検討しています。最終的には、データの提供者、利用者、そしてプラットフォーマーである本学の三者が相互に利益を享受できる「Win-Win」の関係を実現することを目指しています。

J-PEAKS事業のキックオフシンポジウムを開催
―10月23日(木)に、J-PEAKSのキックオフシンポジウム「先端科学技術でリデザインする人口減少社会」が開かれます。どのような内容になるのでしょうか。
中島教授 少子高齢化により生産年齢人口の減少が進む日本で、どのようにすれば大学や企業の研究開発力を強化できるのか、本学のJ-PEAKS事業がその解決に果たす役割を考えようという企画です。まず一般社団法人人口減少対策総合研究所理事長の河合雅司氏が「人口減少社会と大学の役割」をテーマに基調講演を行います。河合氏は、人口減少問題の緻密な分析と解決策を提案したベストセラー『未来の年表』シリーズの著者です。本学J-PEAKSの取組を簡単に紹介した後、パネルディスカッションを行います。パネリストは、基調講演の河合氏、JSR株式会社マテリアルズ・インフォマティクス推進室長の永井智樹氏と、本学の、インドネシア出身のサクティ・サクリアニ情報科学領域教授、新城雅子・教育推進機構キャリア支援部門客員教授、船津公人・データ駆動型サイエンス創造センター長、です。モデレータは、本学の経営協議会の委員で、本学の地元である生駒市ともご縁が深い、株式会社国際社会経済研究所理事長の藤沢久美氏が務めて下さいます。最後に、本学の塩﨑一裕学長と モデレータの藤沢氏が対談形式でパネルディスカッションの総括を行います。
奈良先端大 創立記念日事業 NAIST × J-PEAKS キックオフシンポジウムについての詳細は、こちらからご確認ください。
https://www.naist.jp/event/2025/09/011400.html

10年後を見据えた奈良先端大の将来像
―最後に、J-PEAKS事業で本学がどのように発展していくか。10年後の大学像について語ってください。
中島教授 大学の研究教育や経営にとって少子高齢化の進行は深刻な問題です。10年後に本学が世の中にどのように認められているか、本学のどこに魅力を感じて学生や研究者が来てくれるかを考えることは非常に重要です。その意味で、今回本学が10年後のビジョンを作り、将来の方向を打ち出したことの意義は大きかったと思います。
また、大学の国際化については、日本は対応が遅れがちで、むしろ憂慮すべき事態になっています。海外経験のある研究者なら、自国の出身者だけで研究する状況は想像しがたいですし、欧米の有力な研究室では主宰者も含めてその国の研究者や学生がマイノリティになっているのはごく普通のことです。これは大学の研究力や経営力を最大化し、自国の発展に必要な戦略を最適化した結果として作られたシステムだと思います。本学は学部からの内部進学が無いにも関わらず、博士後期課程の定員を満たし、かつ、その半数が外国出身者になっている状況ですので、すでに国際化が進んでいます。J-PEAKSの資金を活用して東南アジアの学生の組織的なリクルートを一層強化し、さらなる国際化を目指すことには先見性があると思います。新設される人材バンクのマッチングなどで、大学院に進学する日本人学生が減少している流れが改善されることも期待しています。
上久保教授 10年後の本学は、現在私たちが想像する以上に、社会に対して「開かれた大学」になっていると考えています。その背景には、大学に求められる役割の変化があります。かつて研究室は、研究者や学生たちのコミュニティであり、主に「アカデミアの人材を育てる」場でした。しかし今では、それにとどまらず「広く社会に貢献する人材を育てる」場へとシフトしています。これからは、大学という場そのものを社会が直接活用する時代になるのではないでしょうか。
これは、大学に対する社会の期待が変化していることの表れでもあります。「大学の中で何が行われているのか分からない」状態では、その価値は正しく伝わりません。大学は、科学技術を広く社会に理解してもらうだけでなく、誰もが活用できる場へと自らを変えていく必要があります。私はこうした取り組みこそが「科学技術の民主化」であり、それを通じて大学は真に社会に開かれた存在となると期待しています。
私自身が現在参画しているARWITを具現化するための施設立ち上げ事業も、まさにその試みの一つです。この施設では、これまで記録しにくかった研究経験をデータとして蓄積し、将来的にはAIが研究者をアシストする仕組みの構築を目指しています。これが実現すれば、長期の専門トレーニングを受けていない人でも、新たな科学技術の担い手となれる可能性が拓かれるでしょう。
10年後、本学は、この「科学技術の民主化」を推進する中核機関となっているはずです。学内の限られたコミュニティに閉じるのではなく、深刻化する人手不足といった社会課題も背景に、あらゆる人々と共に科学技術を発展させる「プラットフォーム」のような存在へと進化している。私はそう確信しています。
藤井教授 10年後の本学は、人が集まる大学になってほしいと思っています。他大学の教職員や学生はもちろん、企業の人も行きたいと思う大学です。学外の方が「本学は研究レベルが高く、さらに教育環境も素晴らしい。多くのことが学べます」と耳にし、実際に本学で様々な共創が起きているのを見ることで、「新しい成果が期待できるので行きたい」と思ってもらえるのではないかと考えます。そのために我々は新しい学術を進化させる必要があるし、社会実装や社会貢献として社会を向いた活動をしていかなければならないと思います。
東南アジアの留学生の組織的なリクルートは重要な取り組みです。留学生が来てくれて、日本人の学生との間で学術的な議論を高め合うことはもちろんのこと、お互いの食文化を紹介しあうなどの相互理解が起きることも、本学の研究室を見て実感しています。また、我が国では、海外への投資の収益が国内にフィードバックされることで「第一次所得収支」が大きな黒字になる経済構造になっています。このため、海外にグローバルな人材を輩出することを通じて、もっと投資を増やしていく必要があります。さらに、その投資先に日本で学んだ留学生がいて海外と日本との架け橋になってくれるなど、日本の社会にとって重要な位置づけとして海外との共創があると思います。
シミュレーションやAIをはじめとしたデジタル技術と、リアルなものづくりを融合した物質創成研究が私達の研究室のテーマで、私自身はデジタル技術を活用していますが、ものづくりに直結する私達の分野では、デジタル技術を用いたサイバー空間における研究を謡うのみでなく、物質合成や解析まで踏み込むことで魅力が増すと考えています。そこで、大学のホームページなどで、デジタル化されたデータを出し、そのデータを利用して頂くことに加え、リアルなバイオ・物質合成ファウンドリの設備を提供することをアピールしたいと思います。デジタルでの結びつきを契機として、リアルなものづくり研究で協働して頂くなど、本学の様々なところでステークホルダー(関係者)が集まる環境を作っていきたいと思います。
林教授 今回のJ-PEAKS採択を機に、多くの教職員が力を合わせて本学の5年後、10年後を見据えた問題意識を持ち続けることが重要だと思います。そして、その時々に生じる課題に持続的に対応できる組織を構築していく必要があります。
その実現に向けた取り組みの一つとして、3領域の密接な連携が挙げられます。領域間の連携で本学が対応できる課題の範囲を広げることで、これまで社会課題の解決に貢献してきた本学が、その能力をさらに進化させることが期待できます。
実際、今回のJ-PEAKSにおけるARWIT事業は、3領域の研究者が約1年にわたって定期的に議論を重ねて練り上げた構想です。このように時間をかけて議論を深めることで、社会が抱える問題を3領域の知見を融合し、解決する道筋が見えてきました。研究分野の距離が離れているほど方向性を定めるには時間を要しますが、十分な対話を重ねることで、これまでにない新しい方向性を導き出すことが可能となります。さらには、これまで存在しなかった研究領域そのものを確立できる可能性も秘めています。
融合研究を進めるには、研究者同士の継続的な対話が不可欠です。その過程で学術領域が広がり、研究者間の結束も強まります。新たな融合分野を探索する取り組みは、若手研究者が異なる領域の考え方や手法を学び取り、自らの専門性と結び付けて発展させる経験ともなります。学際的な視点の獲得や複数領域との協働を通じて若手研究者に柔軟な発想力を育むことは、次世代の研究リーダーを育成する上でも重要な意味を持つと思います。