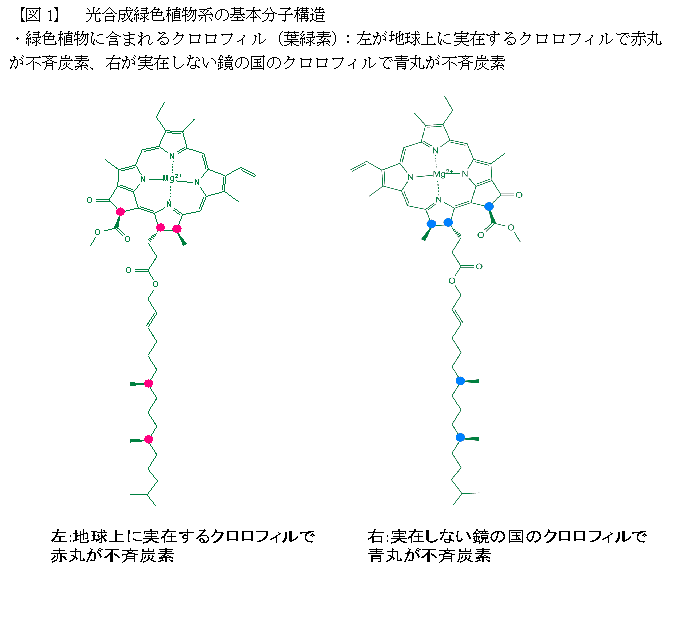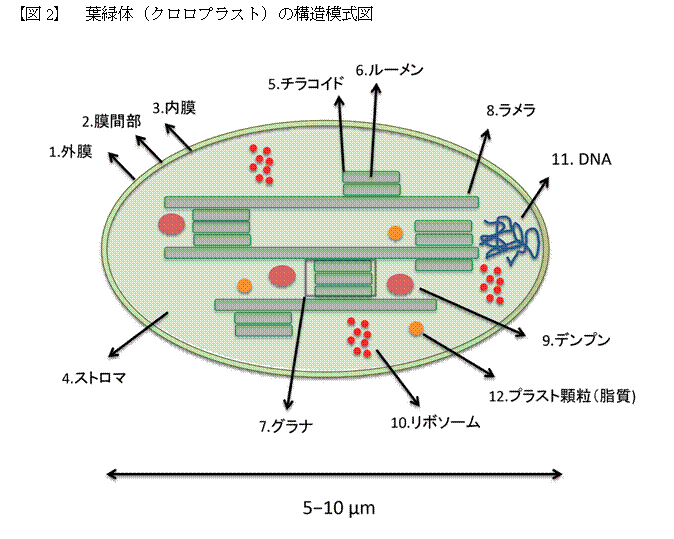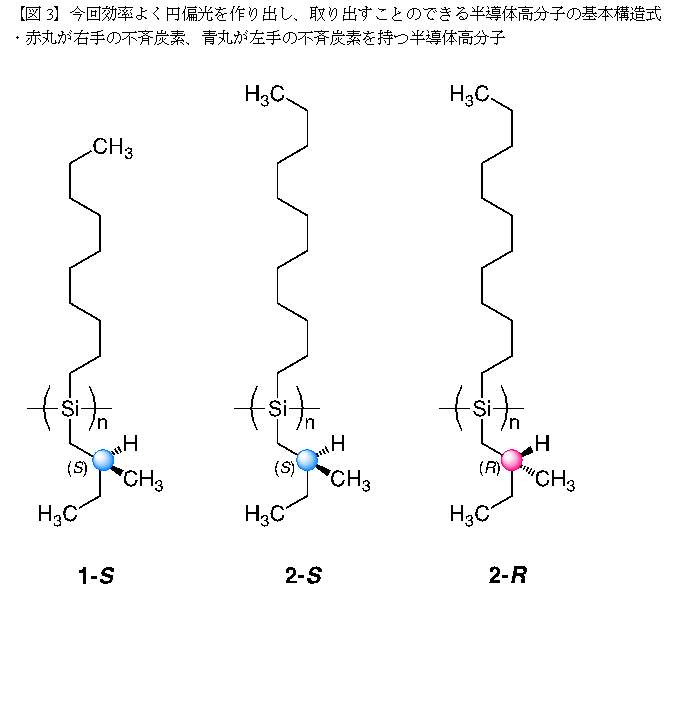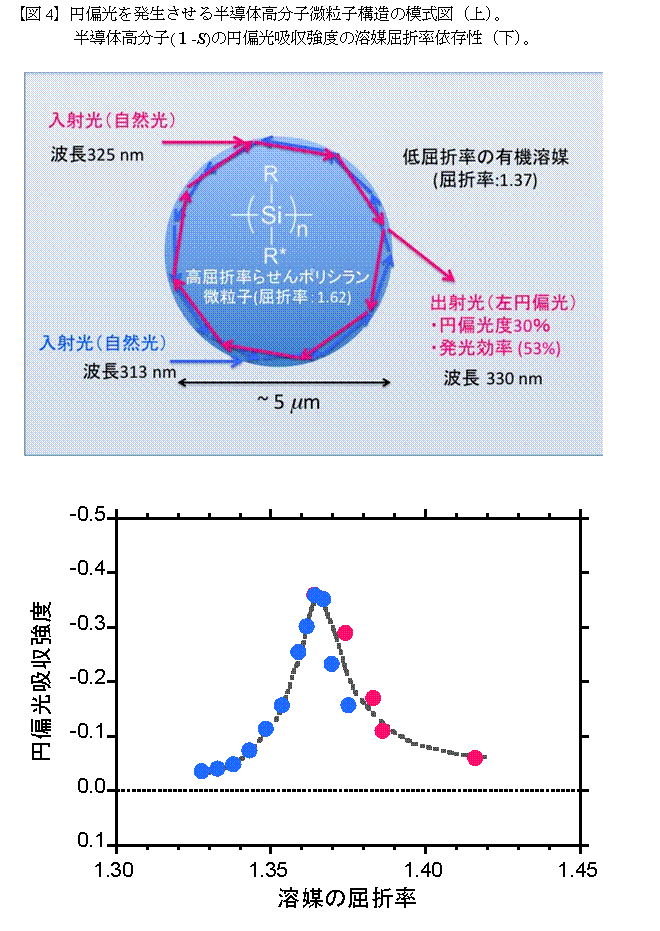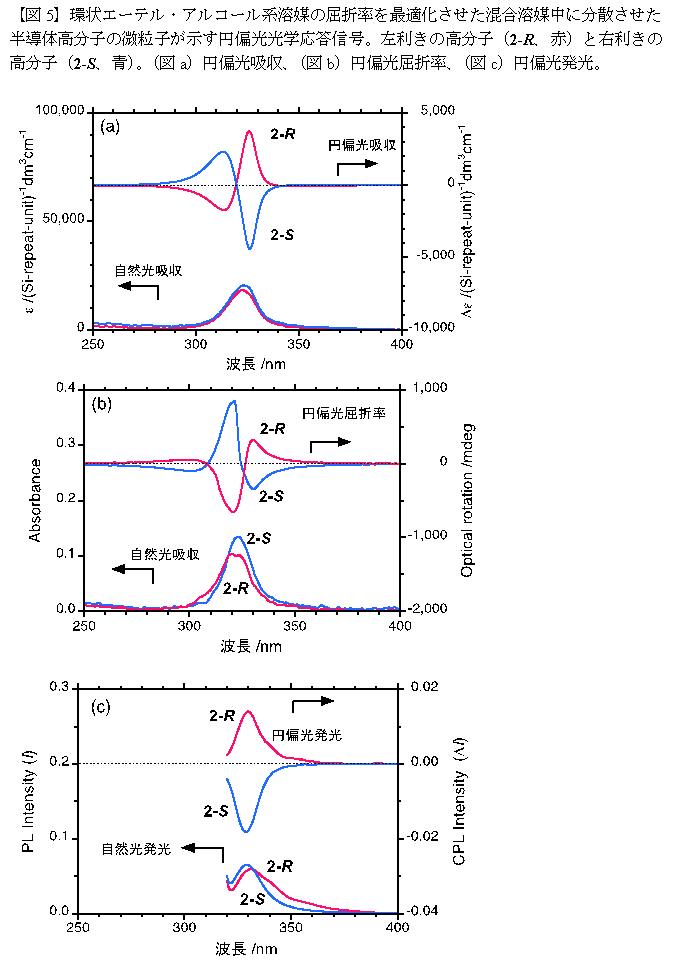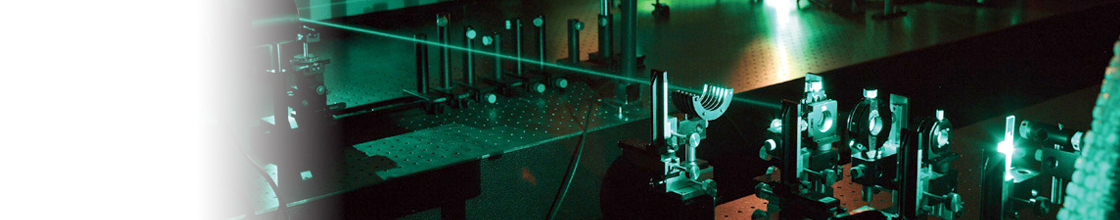2011/09/26
【概要】
太陽光は、右回りで進む右円偏光と、左回りの左円偏光が50:50の割合で混じった自然光と呼ばれる状態で地球上に降りそそいでいる。光 合成を行う緑色植物の構成成分であるクロロフィル(葉緑素)も円偏光を吸収し、円偏光発光を示すことがすでに報告されていたがその役割についてはよく理解 されていなかった。
奈良先端科学技術大学院大学(学長:磯貝 彰)物質創成科学研究科 高分子創成科学研究室博 士課程の中野陽子博士(2010年3月学位取得、現在、オランダ・アイントホーフェン工科大学博士研究員)と藤木道也教授は、ケイ素を主にした高分子半導 体を使い、葉緑体 (図1, 図2)とよく似た環境をつくり、入射した光のエネルギーを吸収して円偏光を高効率で発生させることに世界で初めて成功した。この成果は次世代の光エレクト ロニクスに不可欠な光機能素子材料の開発に大きく貢献するだけでなく、植物の光合成での葉緑体の働きを解明する手がかりとなることが期待される。
中 野さんと藤木教授は「光合成を行う緑色植物も太陽光から左右どちらかの円偏光を発生させ、光合成反応に積極的に利用しているのではないか」との仮説に基づ き研究。ケイ素を主にした化合物に、光学的性質を変えることができる有機分子(有機側鎖基)を結合した「有機ポリシラン」と呼ばれる物質を使い、円偏光を 発生する人工的な半導体高分子に仕立てた(図3)。これを葉緑体の大きさに近い5μmの微粒子を溶液(有機溶媒)中で調製し、円偏光特性などの光学的性質 を詳細に調べた(図4)。
その結果、自然光を試料溶液に入射させると、5μm程度のポリシラン微粒子が優れた円偏光特性を示し、自然光か ら非常に高純度の円偏光吸収と円偏光発光(円偏光純度35%、蛍光量子収率53%)が発生していることを世界で初めて見いだした。光に対するポリシラン微 粒子の屈折率が1.62程度であるのに対して、有機溶媒の屈折率が1.37になった時に円偏光発生効率が最大となった(図4)。また有機側鎖基の化学構造 を少しかえるだけで、左右どちらの円偏光も発生できた(図5)。
葉緑体は2-10μm程度の大きさで凸レンズ状の形態で(図2)、チラコ イドとその積層構造であるグラナ(直径400から600nm、長さ500から800nm)など構成要素の屈折率は1.6前後、液相のストロマ(基質)の屈 折率は1.4前後と予想されることから、葉緑体の光合成機構においても同様の仕組み(円偏光閉込効果)が関与しており、太陽光から左右の円偏光を効率よく 発生させ、光合成反応に利用しているのではないかとの新説を提唱した。
また、入手容易な種々の紫外・可視吸収を有する高分子や分子にも適 用可能で、特別な波長板など固体光学素子を使うことなく、高効率の円偏光の簡便発生と簡便分離を可能にする偏光液体素子を常温常圧下で作製することが容易 になるため、安全性と操作性に優れている。また使用したポリシランや溶媒はすべて回収して再利用できるので、短工程かつ経済性に優れているなど低炭素化社 会に相応しい環境調和型の光機能性高分子の創成技術が実現すると期待される。
この研究成果は、平成23年9月16日以降、間もなく、アメリカ化学会が発行する高分子科学の学術専門誌であるMacromolecules電子版http://dx.doi.org/10.1021/ma201665nに掲載される予定である。
【解説】
◎生命体は左利き、右利き、どちらかの構造の分子や光を利用している
地 球上に住む生命体はすべて、右あるいは左の構造からできた分子からできている。例えばアミノ酸は左利き、糖は右利きである。フラスコの中の反応では鏡像異 性体と呼ばれる左利き、右利きの分子が等量できるにも関わらず、生命体は左右分子のどちらかしか利用していない。鏡の国のアリスが経験したように、現実世 界の分子と鏡の世界の分子では、味も匂いも全く異なる。光の世界でも右と左が存在し、それぞれ右円偏光、左円偏光と呼ばれ、今話題の3次元テレビの立体視 効果を得るのにもその特殊な偏光が使われている。生命分子が左右2タイプのどちらかを使うことについては科学者の間では生命ホモキラリティーの謎と呼ば れ、19世紀後半フランスのルイ・パスツールの時代から150年以上続く未解決の問題とされている。その起源は、遠く果てしない宇宙に存在する円偏光光 源、左利きアミノ酸を含む隕石落下、素粒子レベルの弱い非対称力(CP対称性の破れ)、光速で飛び出す回転するβ電子、コリオリ力(北半球は右向きの力 が、南半球では左向きの力が働く)、全くの偶然だとするものなど諸説がある。
動物の中には、ホタルの尻尾から放たれる発光が円偏光であること (H. ワインバーグら, Nature, 1980, Vol.286, 641 )、シャコの目は円偏光を識別していること(T.-H. チョウら、Current Biology, 2008, Vol.18, 429)、黄金虫の羽は円偏光を反射しているなど (V. シャーマら, Science, 2009, Vol. 325, 449)、理由は未解明ながら円偏光特性を巧みに利用していることがすでに知られている。
一 方太陽光は自然光と呼ばれる右円偏光、左円偏光が50:50の割合で混じった状態で地球上に降りそそいでいる。光合成を行う緑色植物の構成成分であるクロ ロフィルも円偏光発光を示すことがすでに報告されていたがその役割についてはよく理解されていなかった(I. Z. シュタインバーグ, Annual Review of Biophysics and Bioengineering, 1978, Vol.7, 113)。今から半世紀ほど前に、海藻の光合成能力は右円偏光の太陽光が左円偏光のそれよりも大きいことが報告されていた(G. C. マクレオド, Limnology and Oceanography, 1957, Vol. 2, 360)。今年になって豆科の植物では逆に、左円偏光の太陽光が左円偏光のそれよりも大きく生育することが報告された(R. P. シバエフら, International Journal of Botany, 2011, Vol. 7, 113)。そこで光合成を行う緑色植物も太陽光から左右どちらかの円偏光を発生させ、光合成反応に積極的に利用しているのではないかとの仮説に基づき、本 研究を開始した。そして地球上に存在しない鏡の世界の緑色植物で起こっている出来事を垣間みようと思った。
◎光合成と円偏光の関係は
光 合成を行う緑色植物の葉緑体(クロロプラスト)は一般に5−10μm程度の大きさでかつ凸レンズのような形状をとっている。葉緑体を構成するクロロフィル 分子(葉緑素)(図1)では、環周辺部に立体異性をつくる不斉炭素が3箇所、1本の長鎖側鎖基には不斉炭素が2箇所が存在している。ここで図1左側のクロ ロフィル分子は地球上に天然に存在する現実世界の分子であるが、右側のクロロフィル分子は天然に存在しない鏡の世界の分子である。
天然型クロロ フィル分子はさらに約1億個(108)集まってできた規則的な階層構造(チラコイドとその積層構造であるグラナ、グラナ間を連結するラメラ)をとっている (図2)。それらの構造を、金属イオン、酵素などを含むストロマと呼ばれる水溶液で囲まれて存在している。葉緑体がなぜ5μm程度という大きさなのか、な ぜクロロフィル分子が5カ所もの不斉炭素を必要とするのか(図1)?なぜ巨大な数が集まって凝集体を形成しているのか?(図2)、なぜ太陽光の強さや温 度、ストロマ中のイオン強度(Mg2+/K+)によって光合成能力自律的に調節されているのか?、なぜ自然光である太陽光を使って効率よく光合成できる か?ストロマには何か特別な役割があるのか?これらの疑問に対し、種々の仮説を検証するための実験の実施が困難で、十分に明らかにされていたとは言えな かった。
◎葉緑体をまねた環境で実験、高効率で円偏光を発生
そこで、中野氏と藤木教授は、有機ポリシランと呼ばれる直径 0.2nmのケイ素主鎖骨格と長さ1nmの有機側鎖基、全長70nmのからなる人工的な半導体高分子を使って(図3)、大きさ5μmの微粒子を液相中で調 製し、円偏光特性などの光学的性質を詳細に調べた(図4)。その際、有機側鎖基の構造を少しかえるだけで右利きと左利き構造ができ、現実世界と鏡の世界の 高分子を比較することができた(図3)。また溶媒の組成や屈折率を連続的に変化させることができた。
ポリシラン微粒子の試料調製操作は、すべて常 温常圧下、液相で行うため、安全性と操作性に優れている。有機ポリシランの環状エーテル溶液にアルコールを加え、直径約5μmの微粒子が合成収率 100%、わずか数秒で生成してくる。使用したポリシランは100%回収できるため試料のロスが全くない。使用した溶媒はすべて再利用できるので、短工程 かつ経済性に優れている。低炭素化社会に相応しい環境調和性に優れた光機能高分子の創成技術である。
最近、量子コヒーレンス、量子ビート、確率共 鳴、量子閉込といった固体物理や量子光学などの概念が生命活動の担う可視光吸収性分子でも観測されているとの報告が相次ぎ、大きな話題になっている(E. コリーニ ら, Nature, 2010, Vol. 463, 644, G.S. Engelら, Nature, 2007, Vol. 446, 782)。今回我々は、固体物理や光物理の分野で最近広く知られるようになってきたスローライト、光閉込効果などが、葉緑体の光捕集機能や電荷分離機能に も関わっているのではないかとの作業仮説のもと、不斉側鎖基を有するポリシランのμmサイズ凝集体を作製し詳細に検討してきた。その結果、粒子サイズが 5μm程度のポリシラン微粒子が優れた円偏光特性を示し、自然光から非常に高純度の円偏光吸収と円偏光発光(円偏光純度35%、蛍光量子収率53%)が発 生していることを見いだした。そしてポリシラン微粒子の屈折率が1.62程度であるのに対して、有機溶媒の屈折率が1.37になった時に円偏光発生効率が 最大となった(図4)。側鎖である化学構造を少しかえるだけで、現実世界と鏡の世界である左右どちらの円偏光も発生できた。世界で始めて得られた成果であ る。
◎葉緑体の光合成機構に新説
低屈折率の有機溶媒(オプトフルード)中に高屈折率であるポリシラン凝集体を分散させることによ り、自然光が試料溶液に入射すると、特定の屈折率を有する有機溶媒組成において、左右の円偏光が非常に効率よく閉じ込められ、左右円偏光が分離していると の結論を得た。すなわち短波長側の紫外光は左回り円偏光が遅くなり、長波長側の紫外光に対しては右回り円偏光が遅くなり、その結果として、自然光エネル ギーがすべて右円偏光となって高効率で非常によく発光するという仕組みである。
本知見から、葉緑体においても5-10μm程度の大きさであり、チ ラコイドとその積層構造であるグラナなど構成要素の屈折率は1.6前後、ストロマの屈折率は1.4前後であることから、葉緑体の光合成機構におても同様の 円偏光閉込効果が関与しており、太陽光から左右の円偏光を効率よく発生させ、光合成反応に利用しているのではないかという新説を提唱した。自然光でかつ非 コヒーレントな太陽光を使った光合成系の光捕集や電荷分離機構に新しい描像を提供できるのではと期待している。
◎次世代の光機能素子開発へ
最 近、Optofluidic (オプトフルーディック)という造語が生まれた(D. プサルティスら, Nature, 2006, Vol. 442, 381)。光学素子をリジッドな固体材料ではなく、設計性にすぐれた液体材料に置き換えた新概念の光学システムとして近年注目を集めている。固相と液相の 界面や液液界面の平滑性を簡単に引き出し、複数の分子組成からなる相溶性溶液の濃度勾配を持つフロー反応系などの光学設計が容易にできるなどの優れた特徴 を有している。これまでに、屈折率マッチングさせたオイルイマーション光学顕微鏡、巨大な液体反射鏡を用いた望遠鏡、液体コアの光学ファイバー、固体・電 解質界面における接触角が外部電場で変化する電気湿潤効果による可変焦点液体レンズなどとして知られていた。自然光から効率よく円偏光を取り出す技術が可 視光・赤外光・電波の領域で開発されているがいずれも非常に高度な微細加工技術や職人芸のノウハウ、高価な真空装置などを必要としている。
本知見 はまた入手容易な種々の紫外・可視吸収を有する高分子や分子にも適用可能で、固体光学素子を使うことなく、高効率の円偏光の簡便発生と簡便分離を可能にす る偏光液体素子を常温常圧下での作製が可能となる。通常、円偏光を発生させるには、バンドパスフィルター、直線偏光板、波長板(λ/4)という三つの固体 光学素子を必要とするが、Optofluidicの手法の概念を利用すれば、太陽光のような自然光でかつ非コヒーレントな光でよい。実際に、光合成を行う 植物にはそのような素子を持ちあわせていない。
液体中に分散させた数μm程度の光学活性高分子凝集体は、円偏光閉込め効果を利用した素子設計の自 由度が飛躍的に大きくなる。高効率の光電変換や光熱変換の素子材料設計にも活用できよう。将来、屈折率マッチングをとったプラスチックフィルムや高分子ゲ ルなどが利用できるようになれば、取扱いが容易な新しい偏光分離素子材料として利用できるようになるかも知れない。
【関連リンク】
・論文は以下に掲載されております。
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ma201665n
・以下は論文の書誌情報です。
Nakano, Yoko; Fujiki, Michiya. Circularly Polarized Light Enhancement by Helical Polysilane Aggregates Suspension in Organic Optofluids. MACROMOLECULES. 16 September 2011