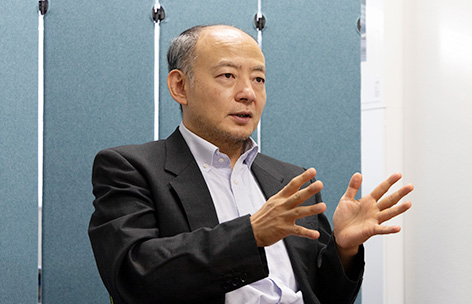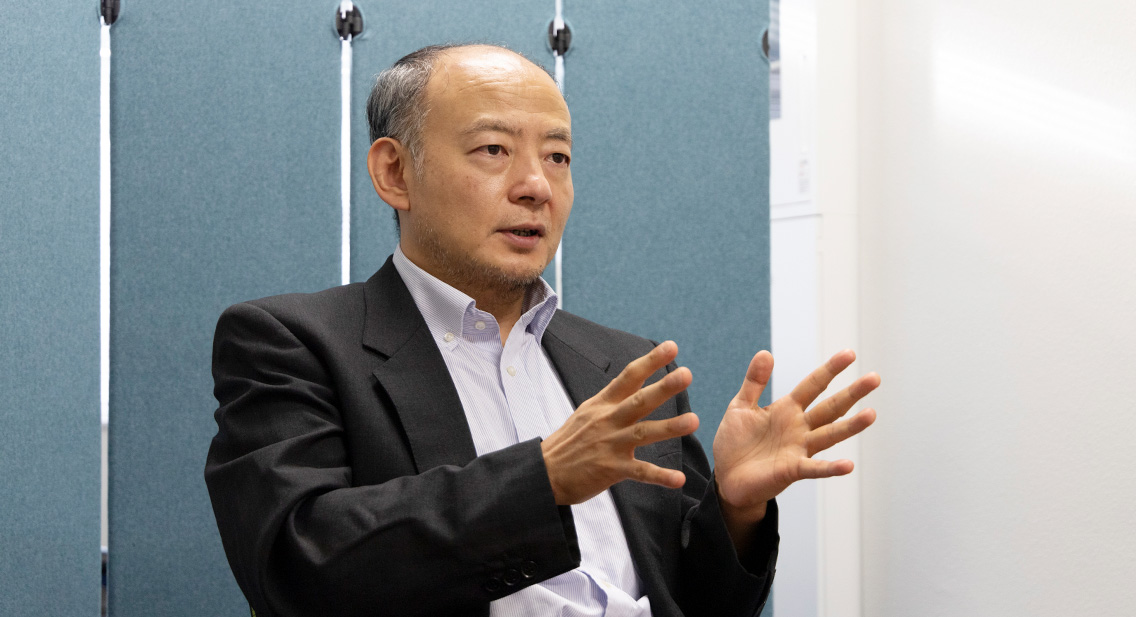
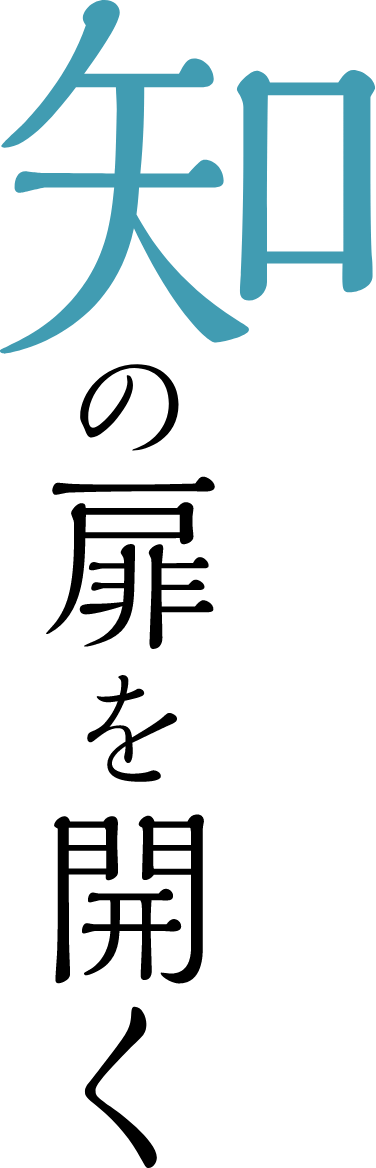
数値データに寄り添い、生命活動の本質を明らかにする
定量的に解析して推定
生物の体(組織)は、さまざまな細胞が集まって作られ、それらは連携しながら生体内外の環境の変化に柔軟に対応して生きています。その複雑で、したたかな生命活動の仕組みを解明するため、生物実験や観測から得られる膨大な数値データから数理モデルをつくり、定量的に解析し推定するのが「データ駆動型生物学」です。作村教授は、細胞の移動の際に生じる「力」など物理データを駆使した研究で知られ、呼気に含まれる成分から病変を自動的に診断する研究など医学への貢献も期待されています。
「基本的に実験系の研究者と共同研究することが多く、議論を重ねながらデータを解析しています。提供された実験の画像データなどから数値化したデータを取りだし、AI(人工知能)の機械学習を適用したり、数式で表現する数理モデルを作ったりして、細胞内の分子間の関わりを見出すのです」と作村教授。
精度を高める
数理解析の研究は、金属など物質を対象にする場合は、構成する元素の物理的、化学的な特性を表す基本のデータベースを使うことで、効率的な反応の道筋などを推測します。ところが、生体のシステムは、細胞内で多様な分子の反応が同時並行に起き、互いに関連して現象を生み出しているので、特定の分子と現象(表現型)の関わり合いのルール(法則性)がなかなかつかめません。このため、実験の経過に沿って撮影した複数枚の画像などから実測値に相当する連続した数値データを弾き出し、推定の精度を高める研究が行われていますが、技術的に個々の分子をまとめて同時に観測することができないという大きな課題がありました。
そこで、作村教授が力を入れているテーマは、個別の分子のデータを加工して、同時に観測したとみなせるデータに変換し、実際に起きている現象を数理モデルの数式で表現するというこれまでにない発想の研究です。ヒトのがん細胞の移動を複数の分子が協調して制御しているケースを題材に、細胞の移動に伴う形態の経時的な変化と、その周辺に存在する複数の分子の動向をまとめて関連づける研究を行っています。
そのなかで、新たな成果は、細胞内で情報伝達の分子スイッチの役割を果たす3つの Rho ファミリーGタンパク質(Rho GTPase)の活性度を細胞エッジ(周縁)の変形速度として定量的に変換する数式の導出に成功したことです。この数式により、ヒト線維肉腫由来のHT-1080細胞において、これら3種の分子が細胞変形を説明するのに十分な情報を持っていることを数値的に証明するとともに、細胞変形に対してこれらの分子がどのように協調しているのかを解明しました。
また、細胞が形を変化する際に生じる力は直接測定できませんが、細胞が乗った培地(培養基質)が、細胞の形態の変化した場所で歪む度合いから逆算して力を推定するという研究も続けています。
呼気から病変をつきとめる
一方、呼気に含まれる血液成分のデータを、AIの機械学習で自動的に解析し、肺がんなど複数の病気を初期段階で見つけることができる診断システムを大学医学部などとの共同研究で開発しています。これまで、肺ガンでは90%以上の精度で診断できることがわかり、少量の呼気でも診断できる高精度の検査器や診断アルゴリズムの開発に加えて、呼気成分により有効な治療法を選択できる可能性など将来の医療の問題にも踏み込んで研究しています。作村教授は「肺がんのほか、肝がん、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)、歯周炎についても調べています。医療関連のビッグデータを処理するのは医師でも限界があり、医療現場をサポートできるような有効なアルゴリズムを開発していきたい」と語ります。
「データ駆動型生物学の研究は、いかにデータに寄り添うかにかかっています。その分野の背景を確実に習得するまでは、苦しい茨の道ですが、そこから何か新しい役立つ結果を引き出せると思います」と作村教授は断言します。これまでの研究の道筋からも物理学から生物学まで幅広い分野に柔軟に対応してきたことがうかがえます。宇宙物理学を志して大学に入りましたが、当時急速に発展していた脳神経細胞の数理モデルの研究を手掛けるようになり、奈良先端大では、神経細胞の突起が伸長して「極性」を形成する機構の研究で知られる稲垣直之教授との出会いから、その現象を説明する定量物理モデルの作成に成功しています。「奈良先端大での共同研究をきっかけにさまざまな分子生物学のデータを扱うようになりました。生物学であっても力学という好きな物理の分野の議論ができることが楽しく、物理学を学んでいた意味があったと思う」と作村教授は話します。

小鍛治 俊也 助教
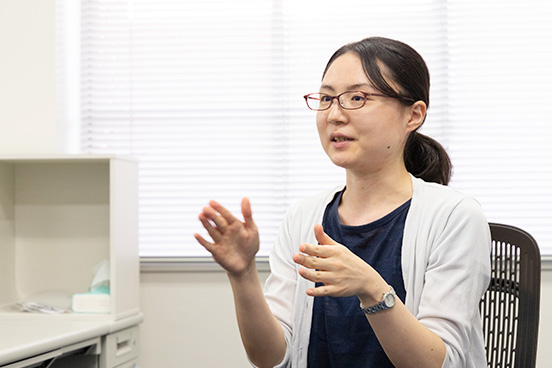
田川 晴奈さん
ビッグデータを解析する
小鍛治助教は、肝臓で糖が代謝されて生成したグルコースが血液により筋肉に送られ、エネルギー源として消費される過程で起きる分子の制御の機構を研究しています。代謝の段階ごとに関連する分子を同時計測した膨大なデータ(オミクスデータ)をもとに全体像を浮き彫りにするトランスオミクス解析という手法を使い、野生型マウスと肥満モデルマウスとを比較して、それぞれの肝臓と筋肉の状態を調べました。その結果、肥満マウスでは糖代謝物を血液に運ぶ輸送体や代謝酵素の異常がみられ、肝臓と筋肉の血液を介した臓器連携がうまくいかず高血糖症を起こしている可能性を明らかにしました。
「トランスオミクス解析はビッグデータを扱うので解析が大変ですが、それだけに新たな仮説が立てられる知見も見つかりつつあります。インパクトのある仮説を発表して検証し、さらに拡張した規模のデータ解析を行うというループを自分に課していきたい」と小鍛治助教は抱負を語ります。「奈良先端大は共同研究の機会が多くあり、研究のネットワークも広がりました」。
研究室の学生も積極的にテーマに挑んでいます。博士前期課程2年生の田川晴奈さんの研究は、脳の腫瘍細胞のグリオーマ(神経膠腫、しんけいこうしゅ)の形の変化と力の測定です。この細胞が脳の組織に浸潤するときに形成する突起の機能について、画像情報から数理モデルをつくって調べており「脳内の環境によって細胞の移動の仕方が異なることがわかりました。研究を続け、グリオーマの浸潤を抑制する条件をみつけて医療に役立てたい」と意欲をみせています。