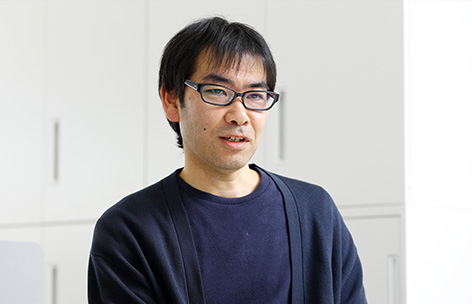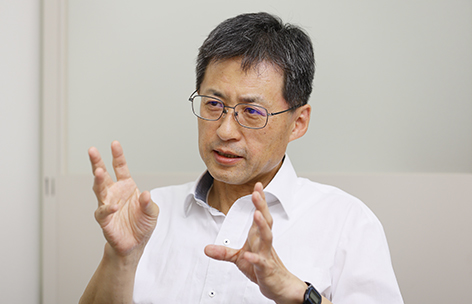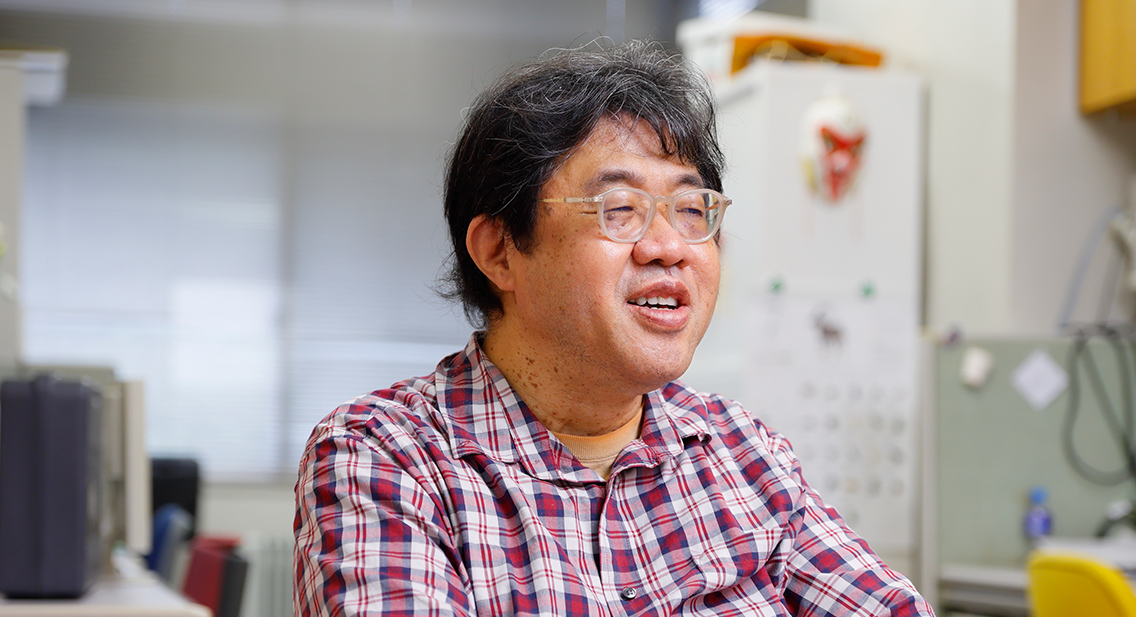
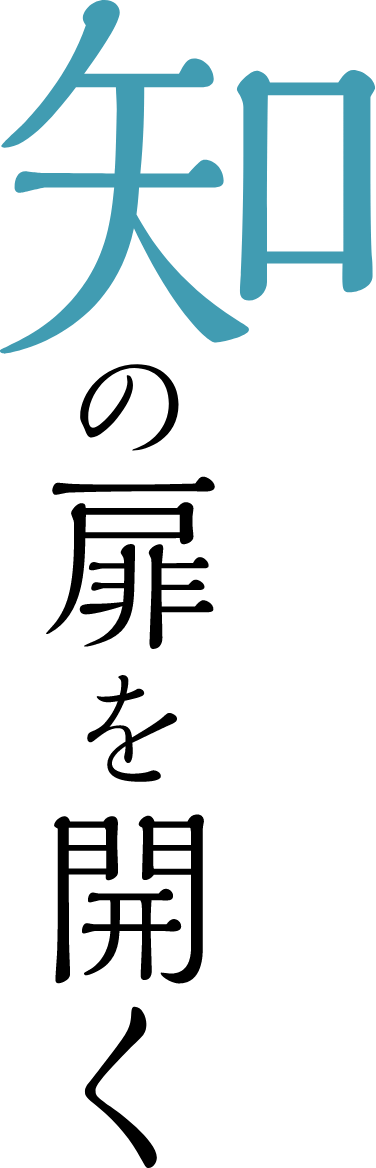
酵母のストレスを解消し、良質なたんぱく質の生産性を向上する
小胞体の異常を感知するシステムを解明
生物の細胞内の核の周囲には、タンパク質を合成、輸送する「小胞体」をはじめ、エネルギーを生産する「ミトコンドリア」など多種類の細胞小器官(オルガネラ)が取り巻く形で配置されています。それぞれ機能分担して連携し、生命活動を支えているのです。
木俣准教授は、異常な形のタンパク質の蓄積のために小胞体の生理機能に悪影響が生じる「小胞体ストレス」に陥ったときに、自己防衛して回復する「小胞体ストレス応答(UPR)」の機構について、モデル酵母のサッカロミセス・セラビシエを使い研究しています。これまでに小胞体が異常なタンパク質を感知してUPRを発動する際の詳細な仕組みを明らかにしました。さらに、小胞体に恒常的にUPRを発現させて脂質など有用物質の生産を行わせる研究も進めています。
木俣准教授は「酵母は単細胞の微生物ですが、動植物と同じ膜に包まれた核を持つ真核生物であり、培養や実験がし易いため、他の生物に先行して生命活動の基礎研究に使われるケースが増えています。応用面ではUPRの仕組みを利用して有用な物質生産の能力を人工的に強化するという手法の開発に結びつきます。今後は認知症など小胞体ストレスが関係するとみられる神経疾患についても調べていきたい」と抱負を語ります。
恒常的にガードする人工の手法
小胞体は、細胞の生理機能の維持に必要とされる多数のタンパク質の製造工場です。膜で覆われたファイルケースのような袋が連結した構造で、表面に「リポソーム」という遺伝子情報によりタンパク質を合成する構造体が付着しています。そこで合成されたタンパク質分子は、アミノ酸が長い鎖のように結合しており、小胞体の中で、「分子シャペロン」というタンパク質群により、正常に機能する形に整然と折りたたまれたあと、膜に包まれ小胞体の外に運ばれ、分泌されます。
ところが、異常な形のタンパク質が生じて蓄積すると「小胞体ストレス」を起こします。そこで、救済のため、遺伝情報を変更して発動されるのが「UPR」です。「分子シャペロン」などが多く作られ、異常なタンパク質を処理し、ストレスを緩和します。
木俣准教授は、UPRが発動されるときの機構について重要な発見をしています。小胞体ストレスの原因になる異常なタンパク質を膜に埋め込まれたタンパク質「Ire1」が感知すると、「Ire1」は自己会合して巨大なタンパク質分子を形成し、強力なRNA切断酵素になります。その多量体が、分子シャペロンなどの遺伝子を稼働させる転写因子「HAC1」の前駆体の遺伝子(mRNA)を調整してHAC1タンパク質を生じさせることにより、UPRを引き起こすことを突き止めました。 「UPRを起こす仕組みが判明したことで、恒常的にUPRを発現させる人工的な手法の開発にも成功しました」と木俣准教授。
そこで、酵母にHAC1の遺伝子を導入し、恒常的に発現させてUPRを強化したところ、分泌タンパク質や、膜で生合成している脂質の生産性が約3倍に向上しました。さらに、ビタミンAの前駆体で脂溶性の赤色色素「βカロテン」について、他の生物種の合成遺伝子を導入したところ、野生株の約8倍の生産性を示しました。UPRの強化による有用物質の生産性向上の道を拓いたのです。
「小胞体は、整った構造で機能性が高く品質の良いタンパク質を作れます。例えば、食品生産用の酵母を使って、糖尿病治療のインシュリン、感染症予防の抗体など動物由来の医薬品を効率よく作る研究も手掛けていきたい」と話します。
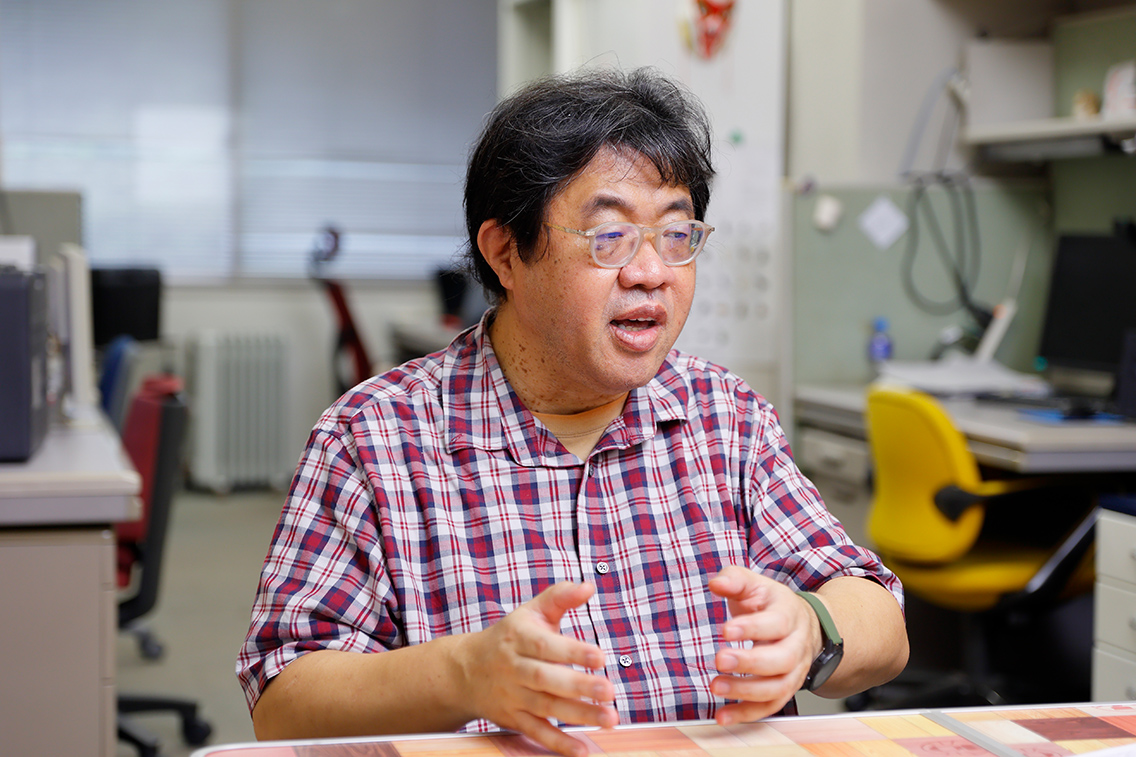
永遠のバックパッカー
木俣准教授は、大阪大学薬学部に入学し、同大学院医学研究科博士後期課程を卒業後、本学に赴任し、酵母のUPRなど小胞体の研究を続けています。今年4月にPI(研究グループの統括者)として「オルガネラ制御生物学研究室」を立ち上げました。
「細胞内の小器官の形づくりや分泌タンパク質の動向に興味があり、研究をはじめました。その当時、動物の細胞と類似した構造や機能が研究できると注目された酵母は、現在も新たな発展性がある知見を提供してくれます」と話します。2018年には、ノーベル生理学・医学賞受賞者の大隅良典博士が設立した「大隅基礎科学創成財団」から、酵母を用いた独創的な研究に与えられる研究助成に採択され、「酵母コンソーシアムフェロー」の称号が授与されました。
研究に対する心構えは「最終的に加工されたデータではなく、生のデータにこそ真の情報がある」。学生に対しても、途中経過の不揃いなデータを大切にするように指導しています。
趣味は「永遠のバックパッカー」を自称するように、学生時代から続けているアジア旅行です。これまでフィリピン、タイ、マレーシアなどの東南アジアやインド、ネパールをめぐりました。「留学生の母国の話をすると、驚かれるほどあちこち踏破しています」。
自分で決められる自由が素晴らしい
研究室に所属する学生は、多くが東南アジアからの留学生です。
ベトナム・ハノイ科学技術大学から来たグエン・ゴク・トランさんは特別研究学生です。大学では、抗生物質に耐性が生じる原因と対策についての研究を行っていましたが、「本学では、脳を委縮させる異常なタンパク質の蓄積が発症の原因とされる遺伝的な神経性疾患について、酵母を使って研究しています。その作用機序を解明し、臨床応用できるところまで頑張りたい」と意欲を見せます。
「本学は自分でテーマが選べ、研究の進め方、時間割が決められるうえ、周囲のサポートが非常に親切なところが素晴らしい。使いたい研究設備が必ずあり、十分すぎるぐらいです。日本で博士号が取れ、就職できればとてもうれしい」と話します。
ベトナムでは通学に時間が取られて忙しいため「眠る」のが趣味でしたが、「日本では本学の中に宿舎があるので余裕があり、自分で料理をしたり、寺社をめぐって御朱印を集めるのが趣味になりました」と、日本で充実した日々を送っているようです。

グエン・ゴク・トランさん