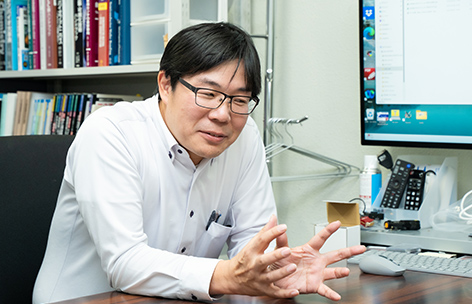バイオサイエンス領域
分子医学細胞生物学研究室
准教授
西村 珠子 Nishimura Tamako
細胞膜の突起から生じる微粒子を介した情報伝達機構を解明
細胞は変形して機能する
生物の体を構成する細胞群は、1つずつ細胞膜に包まれて外界と区切られ、細胞内部のエネルギー代謝など、生命の営みが適切に行える環境を保っています。一方で細胞は、必要な物質を取り込むときは細胞膜を凹ませたり、移動するときには膜の表面に足の役割をする突起を作ったりと、必要に応じて自ら柔軟に形を変えます。
このような外界との境界に位置する細胞膜のもう1つの重要な機能として、細胞同士の情報伝達の担い手としての役割が注目されています。分子医学細胞生物学研究室の西村准教授らは、この細胞膜の突起部分が切断されて細胞外小胞(EV)という微粒子を作り、それが他の細胞に受容されると、その細胞の移動が促進されるという機構を初めて明らかにしました。細胞突起由来の小胞は、動物の発生などにおける情報伝達に重要であることが報告されています。また、細胞の突起はがん細胞に多く見られることから、がんの転移などの病態解明や治療にも大きく貢献する成果と期待されています。
西村准教授は「私たちは、細胞がどのようにして細胞膜の形を変えるのかというメカニズムについて調べてきました。細胞が移動したり、隣接する細胞同士が接着したり、そして膜に突起を作ったりするときに、それぞれの挙動に応じて細胞膜は適切な形に変わります。その仕組みを調べる中で、EVを作る過程が判明したのです」と説明します。
細胞膜は脂質分子が膜状に集合した構造なので、それだけでは変形できず、この膜を裏打ちするタンパク質や、繊維性のアクチン細胞骨格の運動する力が必要です。その際、膜の適切な曲がり具合(曲率)を決める型となるのが、膜に結合したタンパク質(BARドメインタンパク質)です。バナナ型に湾曲した分子構造がブロックのように集積して多量体を形成し、この分子の組み合わせにより、自在に膜の曲率を変えられます。この機構については、同研究室の末次志郎教授が最初に解明しています。
実は、西村准教授らが解明した、細胞膜の突起を切断しEVを作る仕組みでも、このBARドメインタンパク質が主要な役割を果たしていたのです。

膜を曲げる結合タンパク質
「細胞がEVを分泌する仕組みについては、細胞内に取り込んだ物質の選別や分解に使われるエンドソームという膜構造に由来する小胞が、細胞外に分泌されるケースはよく調べられていました。しかしながら、細胞膜の突起が切り離されてEVになる仕組みは、意外にもほとんど知られていませんでした」と西村准教授は振り返ります。
そこで西村准教授は、特にがん細胞が細胞突起からEVを分泌するという報告や、BARドメインタンパク質により陥入した細胞膜が、細胞内部の力で切断され小胞を形成する報告があったことから、BARドメインタンパク質の一種で、膜にらせん状に結合して突起をつくる「MIM」により、細胞突起が切断されうると推測されたことに着目しました。
実験では、培養細胞にMIMを活性状態にして発現させてやると、細胞の周囲にMIMが乗ったEVが多く観察され、MIMの活性を下げるとその数は減り、MIMの量とEVの産生量との間に相関関係があることが示されました。次いで、突起の切断に要する外力の測定や、3次元画像を経時的に取得できるライトシート顕微鏡などで調べたところ、切断に要する外力は、血流など体内で生じる流れ程度の強度でよいことが判明し、MIMにより形成された突起が、小胞形成の主因になりうることが分かりました。
さらに、このEVは、Rac1やIRS4という特定のタンパク質を内包していました。EVを受容した細胞では、これらのタンパク質が伝達され、細胞内で機能することで、細胞を移動させる葉状突起が出やすくなり、細胞の移動が促進されました。すなわち、細胞膜付近にあるシグナルタンパク質が、EVを介して、活性を保ったまま、直接受容細胞に送り届けられました。細胞突起由来のEVは、動物の発生過程や、幹細胞の分化制御などにおいて、重要であることが報告されています。本研究により、その情報伝達機構の一端が、明らかになりました。
こうした研究成果は、がんの診断や治療の面からも注目されています。西村准教授は「がん細胞の中でも、悪性であるほど膜の突起を多く出すことや、EVの内容物には、がん細胞を増悪させる酵素やタンパク質が含まれていることが知られています。がん細胞由来のEVの産生を抑制したり、EV積み荷の活性を阻害したりすることで、がんの治療に結びつく可能性があります」と話します。
このほか、特定のタンパク質など治療に役立つ物質を内包し、かつ特定の受容体を発現したEVを細胞に産生させ、このEVを投与して目的の細胞に届けるという、究極の「ドラッグデリバリーシステム(DDS)」の構築など、研究の構想は広がっています。
観察が一番大事
西村准教授は、京都大学薬学部を卒業後、製薬会社に就職しましたが、「研究に専念したい」という思いが募り、退社して神戸大学大学院に入学しました。その後、同大助教、理化学研究所(神戸市)研究員などを経て、2017年に本学に赴任しました。
この間、発生生物学や細胞生物学の分野で、細胞同士の接着や細胞の変形を伴う現象に興味を抱いて研究を続けてきました。「本学でもBARドメインタンパク質が関わる細胞の変形の研究を行っており、これまで手掛けてきた研究とのつながりを生かして研究に取り組みたい」と意欲を見せます。
研究に対する思いは「観察が一番大事」。理研研究員のときに、チームリーダーで細胞間接着分子の発見で世界的に知られる竹市雅俊先生(京都大学名誉教授、理化学研究所名誉研究員)に教えられた言葉です。「まず顕微鏡を覗いてよく観察し、どんな現象が起きているかを想像します。困った時には、ライブセルイメージングで細胞の動きを観察すれば、新たな突破口が開けることがあります」。
子育てしながらの研究生活を続ける西村准教授は、仕事の時間をやりくりする毎日ですが、中学生になった長男が「理科大好き。研究者になりたい。」と言っていることが励みになっています。趣味は菓子作りで、休日に家族が参加して楽しんでいますが、「どうしても実験のようになってしまう」そうです。