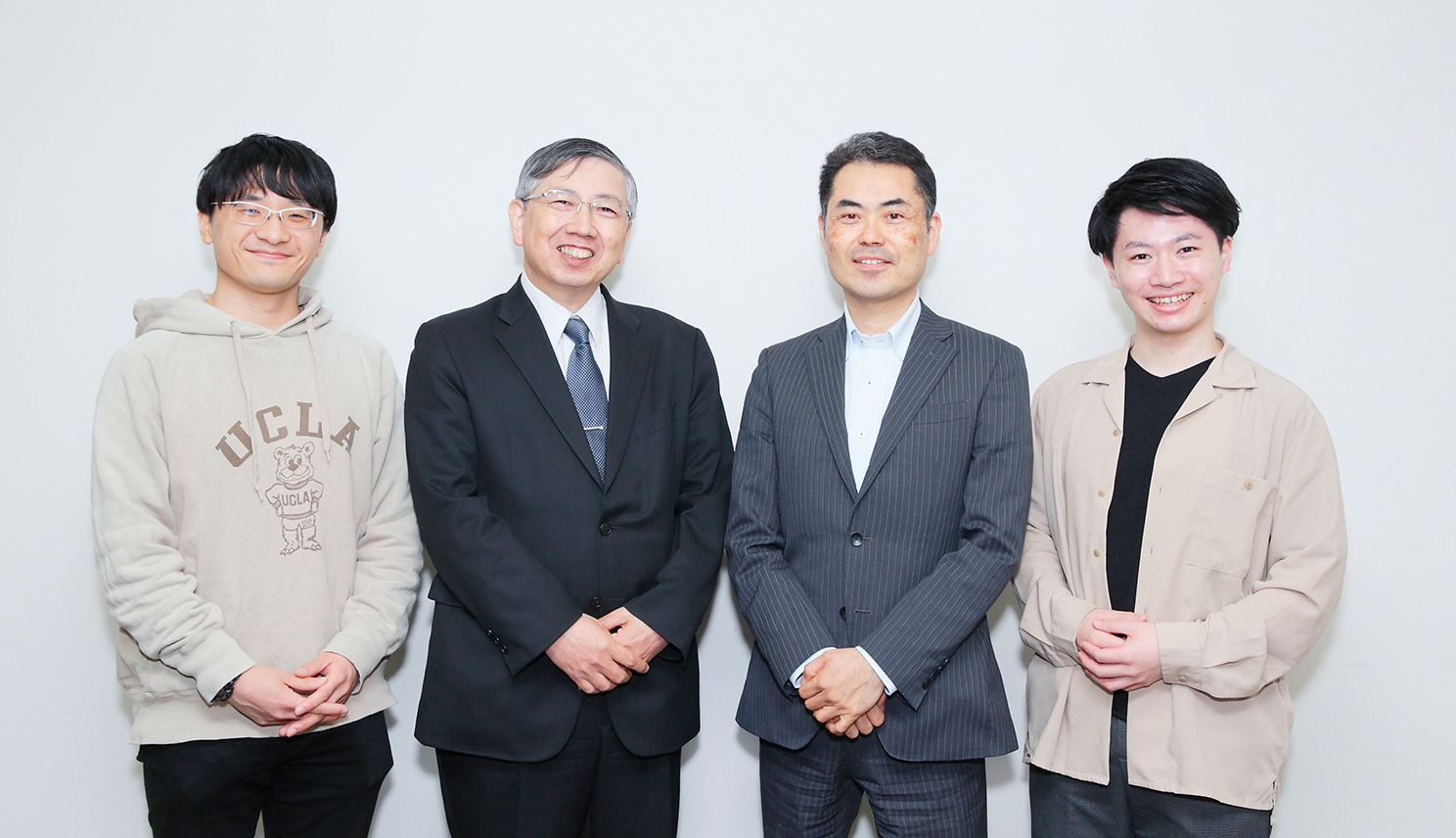

世界をリードするVR・AR研究の国際拠点へ
VR研究で清川教授がIEEEから技術貢献賞を受賞
加藤教授とともにアカデミー創設メンバーに選出
加藤教授とともにアカデミー創設メンバーに選出
清川清教授は、3月に電気・情報工学分野で世界最大規模の学会であるIEEE(米国電気電子学会)の専門部会「VGTC(可視化とグラフィクス技術コミュニティ)」からバーチャルリアリティ(VR)、拡張現実(AR)に関する技術研究の功績を称える「テクニカル・アチーブメント・アワード」を受賞しました。この賞は同じ奈良先端大の加藤博一教授が2009年に受けており、日本人受賞者としては清川教授が2人目です。さらに、清川教授は加藤教授とともに、VGTCに創設された「VRアカデミー」のメンバーにも選出されました。VRやARの研究は、日常生活や働く現場にも大きな変革をもたらす技術として急速に進展しており、今後、奈良先端大が国際的な拠点のひとつとして、研究開発をリードすることが期待されます。
そこで、清川教授・加藤教授に、VR・ARを研究する博士前期課程2年の宮脇亮輔さん、浅田樹生さんがインタビューし、今回の受賞の意義や国際的なネットワーク、本学の研究環境などについて聞きました。
清川教授、加藤教授の業績

清川教授は、メガネのような装置をかけてARの表示画面を見るヘッドマウントディスプレイ(HMD)の研究開発で知られます。目の前の実景に直接CGを重ねる光学透過型HMDは、外光が入るのでCG画像の色が褪せてしまうという基本的な課題について、CGの画素ごとに光の透過度を変調するなどして解決。実環境の映像の奥行の距離を測定しながら、矛盾なく立体CGと混ぜ合わせる装置「ELMO」の開発に成功しました。このほか、状況が把握しやすい超広視野のHMDの開発などを行いました。

加藤教授は、ARシステムを構築するためのソフトウェア「ARツールキット」を1999年に開発しました。当時はカメラで撮影した実画像にCGを重ねて表示するときに、両者の位置合わせをするのは困難でしたが、カメラの位置や姿勢(向き)を識別するパターンが描かれた黒色正方形のマーカーを使い瞬時に計測することで、実画像とCGを違和感なく整合させることに成功しました。オープンソースとして公開したところ、あまりの使い易さから定番ソフトになり、世界中で使われるようになりました。
研究環境に恵まれた
アカデミーの創設メンバーに選出されたことや、「テクニカル・アワード」の受賞について、いまの思いを語ってください。
加藤教授 アカデミーのメンバーは、「テクニカル・アワード」の受賞者や、VR分野に長年貢献してきた人を対象に選考委員の投票で選びます。メンバー49人のうち、日本人は4人と数少ない。なかでも奈良先端大の2人は、現役の大学教授だけに研究の発展に積極的に貢献していきたいと思います。
清川教授 今回の受賞についてはこれまでの論文の引用数から見て評価されたのは、光学透過型HMDのハードの研究(業績の項参照)でしょう。実映像と3次元CGを違和感なく混ぜ合わせることを可能にしました。私は本当に恵まれていて、奈良先端大の大学院生だった90年代後半は、高度な実験装置をパソコンのように使わせてもらえ、ARによる3次元デザインのツールを作るなど、当時前例がなかった研究もできました。でも私と同じレベルの研究をしている人は山ほどいるのに、受賞はありがたいが、恥ずかしい気もします。

清川清教授
未解決の問題に挑む姿勢
宮脇さん 研究の心構えや個性的な発想の源について教えてください。
加藤教授 研究は未解決の問題に挑戦することが大前提ですが、その特徴は2種類あり、「問題を創り出す」と「問題を解く」ということです。私は、未だ誰も解けていない問題を解くのが好きで、その過程で開発した技術が「ARツールキット」(業績の項参照)です。ただ、研究成果について論文を書き、一定の評価を得て終わりにするのではなく、完成度を高めて誰もが使えるように実用化することにはこだわっています。
清川教授 私は「問題を創り出す」方にシフトします。例えば、現実空間と仮想空間の混ぜ合わせが3次元でできる光学透過型HMDは、それまで発想がなかった。開発当初の装置は、映画「スターウォーズ」のダースベーダーがかぶるような不格好さで実用性はゼロでした。しかし、「実用化には10年から30年かかるが、いつか生活を大きく変える。長期のスパンで研究できる大学だからこそすべきだ」という責務を感じていました。
研究テーマによって「成果を誰でも使えるように整える」「無いものを生み出す」という2つの考え方のバランスを取りながら研究することが大切なのですね。
加藤教授 ただ、基礎研究から産業応用までにかなりのギャップがあります。技術関係の論文の審査のときは、同じ分野の博士課程の学生が再現できる成果であれば、学術的には認められる。しかし、産業展開する時には、異分野の人も使いこなせるところまで技術が洗練されなければならない。また、実際に技術を産業に展開するときには、それが本当に役立つのか、副作用はないかなど事前に確認して提示することも大事です。

加藤博一教授
国際的なネットワーク
宮脇さん 海外の研究者と盛んに交流され、国際的な研究者のネットワークを築いておられますが、その秘訣は何ですか。
加藤教授 海外とか、国内とか、あらかじめ意識せずに、トップの実力がある研究者と組みたい。そのため、できるだけ国際学会などに足を運び、その場で研究者と本音で議論して理解を求めることで、交流を深めるようにしています。
清川教授 未知の新しい分野の研究者との共同研究は、実に刺激的です。その意味では、研究のカルチャーが異なる海外の研究者の方が研究を発展させる確率が高く、密なコネクションをつくってきました。2021年度の科研費の報告書だけでも、約10カ国の二十数機関の研究者と共著しています。成果に直結しないケースでも「世界は友達」という感じで、時間を割いて交流するのが喜びにさえなっています。
長期展望に立って
宮脇さん 今後の研究計画について教えてください。
清川教授 これまでのVRの研究の延長としてシフトしたいなと思ったのが、人間拡張、障害者支援というテーマです。ハンディキャップのある人が健常な人と同じように暮らせ、スーパーマンにもなれる。きっかけは日本VR学会で2013年にロードマップ作成の取りまとめ役になったときに、多様性を重視していろいろな立場の人を支援しようという流れになったことです。数十年先の生活に役立つビジョンを描き、そこに向かって研究者がアイデアを出しながら取り組むことは、非常に有意義だと思います。
加藤教授 私のARの研究は20年前に始まり、当初から10年後から20年後を見据えて実用化を目指してきました。つまり、20年が経過した現在は、この技術を実用化する責務があり、AR技術が真に社会に普及するための研究を続けます。また、現在、奈良先端大のデジタルグリーンイノベーションセンターに本務があり、ARなどの情報技術を使い、環境問題など社会課題を解決するイノベーションを起こしていきたいと思っています。

宮脇亮輔さん
体脂肪率3%の研究集団
浅田さん 奈良先端大は研究教育の環境など、どのようなところで優れていると感じていますか。
清川教授 学生にとっては、留学時の支援があり、教員1人当たりの学生数が少ないので指導が手厚いなど非常に恵まれた環境です。使えるチャンスをすべて活用してほしい。教員にとっては、学部がないので、学生実験や入試業務に時間を割かれることは少なく、研究に専念しやすい。アスリートに例えれば、体脂肪率3%まで落として筋肉を付けた集団のように教員がそろって頑張って研究しているので、よい刺激をもらうことが多いです。
加藤教授 奈良先端大は、留学生や外国人教員の比率が高く、英語での講義や学内の至るところで当たり前のように英語で会話する環境があり、グローバルな感覚が身に付きます。事務局からの連絡事項は常に日英併記のメールで行われますが、ある外国人教員は「自国の大学よりも英語が堪能」と驚いていました。また、大型の実験設備やその管理は、格段に充実しています。さらに、学生が独自に企画・推進できる研究プロジェクトを支援する制度「CICP(Creative and International Competitiveness Project)」 などがあり、自由に研究できる環境が整っています。
浅田さん 学生にとっての研究の自由度は非常に実感していて、知りたいことをすぐに学べる環境にあります。CICPについても研究テーマの採択後、スムースに研究資金が提供されたのは、衝撃でもありました。

浅田樹生さん
こだわりと柔軟性
宮脇さん 学生がよい研究リーダーに成長するための資質や日頃の研究姿勢を教えてください。
清川教授 素晴らしいリーダーになりたい人には、こだわりと柔軟性のバランス感覚が必要です。こだわりがないと研究者じゃない。柔軟性がないと多分、どこかでつぶれてしまう。広い視野でアンテナを張り、ここだと思うところを掘り進む。こんな「T字型思考」ができる人は伸びると思います。
加藤教授 絶対に必要なものは、ヒューマンネットワークです。研究者同士が遠慮せず、本音でつきあうことで結果的によい研究成果が生まれると思います。
インタビューを終えた宮脇さんは「国際的に研究が評価され、活躍される先生方の指導を受けることは誇らしいですし、改めて頑張ろうというきっかけをつかみました」と語ります。浅田さんは「未解決の問題を創る、問題を解くという研究のテーマ設定の考え方など吸収して研究に役立てようという向上心がわいてきました」と意欲を見せています。




